先日の鉄博イベント訪問にて
感化されまして常磐線ネタを。
ワタシは茨城県笠間市出身。
表題の件について、
実家近くを走る水戸線との関連などを
含めまして深堀りしてみます。
水戸鉄道→海岸線→常磐線
まずはざっくりと稚拙な手書き図解を
まじえまして、常磐線の歴史をふり返ってみます。
1889 年
水戸鉄道によって水戸に最初に鉄道が到達。
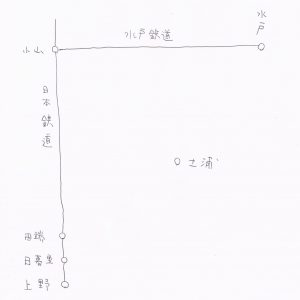
開業区間は小山~水戸。
既に開通していた日本鉄道の駅と
水戸をほぼ最短で結ぶルートで開業。
この区間の内、小山~友部は現在の
水戸線に該当しますが、当時は
友部駅はありませんでした。
1891 年
水戸鉄道、日本鉄道に事業譲渡。
1895 年
友部駅が設置され、ここで分岐し、
東京方面へショートカットする
日本鉄道「土浦線」が土浦まで開通。
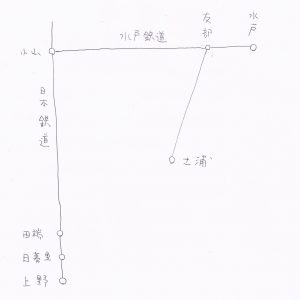
1896 年
土浦線が田端まで繋がります。
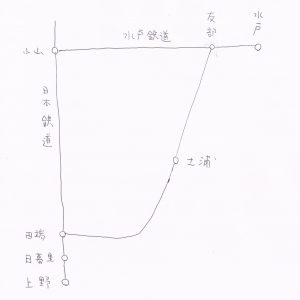
1898 年
水戸~岩沼の磐城線が全通、
現在の常磐線の原型が完成します。
1901 年
田端~友部~水戸~岩沼は、
海岸線に改称され、水戸線は友部が終点に。
この時点で「水戸に行かない水戸線」となりました。
※その名残か、現在でも朝夕を中心に
水戸まで直通する水戸線の列車があります。
1906 年
国有化されました。
1909年
海岸線は「常磐線」へと名称が変わりました。
常磐線の始発駅は
現在、一般的な視点で言うと、
常磐線の始発は「上野」となります。
ただし、これはあくまで列車運転上のお話。
※ 現在は品川まで直通運転していますが、
上野~品川は愛称「上野東京ライン」です。
実際には常磐線の起点は日暮里で、
上野~日暮里は東北本線に属します。
で、先述の歴史の話に戻りますが、
常磐線の東京方のターミナルは
そもそも田端でした。
これは常磐線沿線で取れる石炭を
輸送する貨物列車が当時東海道線の
品川と接続計画があった山手線に
乗り入れるため。
※当時、上野以南は線路が
つながっていませんでした。
その当時、旅客列車は田端で
スイッチバック(方向転換)して
旅客ターミナル駅である上野に
向かっていたそうです。
その後、1905 年には上野方面に
直通できるように日暮里に線路がつながり、
これが現在のメインルートになりました。
先程の概略図に書き足すと、
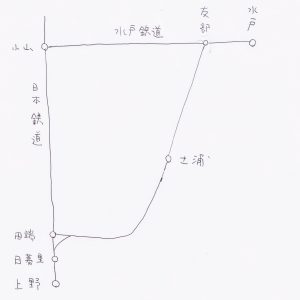
こんな感じに。
日暮里~三河島間で線路が
急カーブを描いているのはこれが理由です。
なお、開業当時のルートだった
田端~三河島の線路は、
現在も貨物線として残っています。
歴史の裏側に
今回はほぼほぼ路線の歴史のみを
さらっとまとめました。
「鉄」な方はこれでも十分ですが、
それ以外の方はその裏に時代背景などに
視野を広げるとまた奥深いものに
なると思います。
したっけ。





